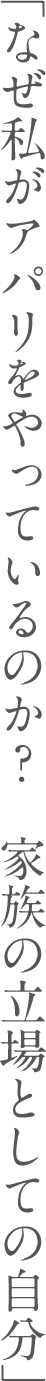
私はアルコール依存症者の家族でした。両親と実家で同居していた弟は18才から43歳までの25年間筆舌に尽くせないほど大迷惑な存在でした。ある会社の正社員として就職し、初めて社会保険証を手にして得意の絶頂にいたのも束の間、酔った挙句に高い場所から足を滑らして転落死しましたが、弟が死んだとき私たち家族には悲しみの感情もなく、これで後の人生は平和に暮らせるとただただほっとしました。涙を流していたのはちょっとの間だけ関わっただけだった私の妻だけでした。
弟は1か月のうち数日しかお酒を飲みませんでしたが、飲むときには1か月分の給料を全部使うような飲み方をしていました。飲んでいないときにもイライラすることが多く、何か気に食わないことがあると、家の中で暴れ、奇声を発しながら部屋や家財道具を破壊し、家族のお金を盗んだり、サラ金の借金を繰り返したりして贅沢の限りを尽くしていました。街に出ても暴れ、地元の飲食店で出禁になったところも多数あり、最期のころはよく地元警察署のお世話になっていました。泥酔してはパトカーで自宅に送り届けられたり、場合によっては暴行罪で逮捕されたりしましたが、毎回起訴猶予になっていました。前科は交通事件の罰金だけだったと思います。母親はいつもその尻ぬぐいに終始していました。まだ貸金業法が制定されていなかったころから借金を繰り返し、自宅に取り立て屋がやってきて、大学教授をしていた母親を脅し、大学に行って、金返せって騒ぐぞと脅したりしていました。そういう時弟はのうのうと寝ていました。私が大学に行くときに取り立て屋と出くわした時には、「お兄さん、家族なら代わりに払ってくださいよ」と言われたこともあります。
私がダルクとかかわるようになった後、覚醒剤乱用者なら警察がすぐに逮捕して刑務所にも入れてくれるのに、問題が酒だと動いてくれない。薬物ならダルクが受け入れてくれて、しかもちゃんとプログラムをやり続けている人は回復している。弟がダルクに入寮して回復してくれたらどんなにいいだろう。いざと言う時に助けを求めたいという気持ちもあったからこそ私は1995年からずっとダルクとかかわり続けていたのでした。
関わり始めた頃の私は家族会の隅の方に椅子を出して家族の話を傍聴させてもらっていました。そのうち、家族会の人たちが、薬物依存者本人が薬物を使っている問題と多額の借金をしている問題に同じレベルで苦しんでいるのを見て、保証人になっていない限り家族には何の責任もないから返済する必要がないこと、本人にとっても、借金問題は最終弁済日から5年経過していれば消滅時効を援用することでチャラにできるし、地方裁判所で自己破産をして免責決定をもらうことができれば、借金がなくなることなどを説明させてもらうようになり、だんだん家族会の輪の中に入っていけるようになりました。
NPO法人アパリ 理事長 尾田真言



